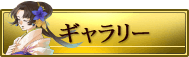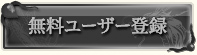<天儀とは>
天儀を一言で表現するならば、『壁に囲まれた浮遊島』と表現できる。
天儀本島やその他諸国の島(儀)は空に浮かんでおり、島間を移動するには飛行手段を用意するしかない。
引力が働く天儀において、なぜ島が浮いているのかは未だもって明らかではないが、
存在する歴史『物語』を紐解けば、精霊の力が安定した水や浮遊力を可能にしているという説と、
古代文明が開発した力によって浮かんでいるという説とが確認できる。
どちらの説が正しいかはともかくとして、
天儀歴1009年現在までに、発見された陸はすべて浮上しており、
かつ、空は見ることができるが水が滝のように落ちる下に何があるかを確認した者はいない。
(飛び降りた者はいるだろうが、いずれにせよ話を伺うことはできないし、今後その者と生きて会うこともないであろう。)
天儀には大きく分けて6国1王朝を有する1つの巨大な儀と、
泰国、ジルベリア帝国という、独自の文化を持つ国がそれぞれ存在する2つの儀がある。
儀や島ごとに気候は多少変化するが、いずれも我々が生活できるレベルの範疇におさまっている。
また、いずれの儀においても、アヤカシの被害に悩まされているという点においても同一である。
<コラム:島と儀の違い>
『天儀本島』などという言葉が指すとおり、言葉が乱れがちな昨今、
天儀の世界において「島」と「儀」はしばしば混同されがちであるが、そもそも別のものである。
島と儀の違いは、簡単に言えば海に浮いているか空に浮いているかの違いである。
基本的に儀の内部に島は存在する。儀は海をたくわえるが、島が海をたくわえることはない。
また、島の外は基本的に海が存在し、船での航行が可能だが、
儀の外は断崖絶壁となっており、移動するためには飛空船が必要である。
<コラム:水はどうなっているのか?>
天儀の俯瞰図を見た際に誰もが疑問に考えるであろう事柄について、本項目では述べていきたいと考える。
儀の外が断崖絶壁である天儀において、海や川を経てその場所に達した水は、もちろんその場から落下する。
その光景が特徴的であるので、見た者が水不足に対して懸念することも不思議ではないが、
落ちた水は儀の下部に存在する嵐の壁に阻まれ、それ以上落ちることはなく、雲となり雨となって天儀に戻ってくるようである。
また、天儀の端は基本的に隆起しており、落ちる水の量は見た目に感じるほど多くなく、
少なくとも天儀本島において、水が完全に枯れてしまうような事態はまず発生しない。
このため、地形の形及び下部の嵐の壁までもが我々の望むような形になっていることを精霊の奇跡と呼ぶ者も少なからず存在するが、
なに、気にすることはない。望むような形でなかったら、我々はそもそも存在しないのであるから‥‥
<天儀本島データ>
儀の直径 : 3500km程度
有する国 :武天(ぶてん)、陰殻(いんがい)、朱藩(しゅはん)、東房(とうぼう)、理穴(りけつ)、五行(ごぎょう)、天儀王朝(テンギオウチョウ)